質問ランキング トップ5
1位国民負担の軽減
-
 Q
Q国民の負担を減らすには、どのような取組みが必要だと考えていますか?
Aまずは行政手続きの簡素化や契約の見直しによるコスト削減など、徹底的な効率化が必要です。8年の市長としての行政経験を活かし、まずは無駄な支出を削減し、家計への負担を軽減してまいります。
2位持続可能な社会保障
-
 Q
Q社会保障や年金制度について、どのような課題を感じていますか?
A年金をはじめとする社会保障制度が非常に複雑化し、国民にとって分かりづらくなっていることが大きな課題です。社会保険料が年々上がり、給与から天引きされていく一方で、その仕組みが国会で十分に議論されずに進められている現状を変えなければなりません。安心感や信頼感のある社会保障を実現するためには、抜本的な見直しにより分かりやすい制度とし、負担と給付のバランスを国民が納得できる仕組みに変えていくことが重要だと考えています。
3位企業・団体献金ゼロ
-
 Q
Q政治とお金の問題が尽きません。企業や団体からの献金をどう考えていますか?
A企業・団体献金を完全に禁止すべきです。政治が本来あるべき姿を取り戻すためには、資金面でのしがらみを断ち切る必要があります。特定の利害関係者から多額の献金を受け取っていれば、どうしてもその影響を受けざるを得ません。だからこそ「企業献金ゼロ」を実現し、国民の皆さん一人ひとりからの小口寄付で支えていただく透明な政治を目指します。
4位しがらみのない候補者
-
 Q
Q政党に属さず「無所属」で政治活動をすることに不安がありますが、本当に政治を変えられるのでしょうか?
A私は、政党のような「しがらみ」を持たないことを大切にしています。無所属で活動するからこそ、団体や組織の利害に縛られず、国民の皆さん一人ひとりにしっかりと向き合うことができます。今回の挑戦が、無所属で戦う政治家が各地で現れるきっかけとなり、その流れが社会を変える力になると信じています。
5位外国人対策
-
 Q
Q外国人の増加に対してどんな対策が必要だと考えますか?
Aまず事実として、すでに日本が年間数十万人の外国人を受け入れている「移民大国」であると認識することが必要です。その上で、「我が国に移民はいない」という政府の立場を改め、適正な出入国管理に加え、在留・就労・住居・教育をまとめて管理する「外国人マネジメント窓口」の整備が不可欠です。
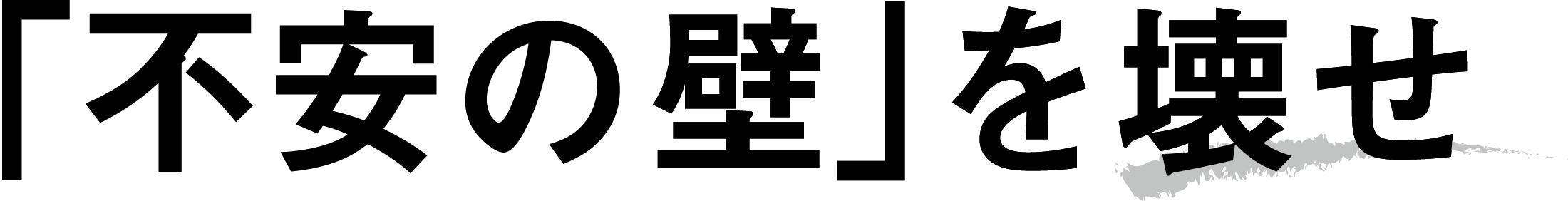
-
Q
年金だけで老後は安心して暮らせますか?
A
年金財政を重視した結果、目減りが続く現行の年金制度では、老後に安心して生活することは難しいと考えています。
そのため、物価と連動して底上げされる「最低保障年金」を確立し、年金の「財政」ではなく、年金による「生活」を守る制度への転換が必要です。
また、年金は本来「仕送り方式」(賦課方式)で、現役世代が高齢者を支える仕組みでしたが、人口ピラミッドの変化により若い世代が減り、仕送りだけでは支えきれなくなっています。
そもそも、私的年金である3階部分(確定拠出年金など)がなければ老後生活が成り立たないという公的年金の現状に、私は大きな違和感を覚えています。
今後は、積立方式への段階的移行などを着実に進め、受給不安の解消に取り組むべきだと考えています。
-
Q
社会保障について、これからどう改善していくつもりですか?
A
私は、社会保障に対する「不安の壁」を壊すことが、最も重要だと考えています。
現状では、年金をはじめとする社会保障制度への信頼が失われており、それが暮らしへの安心感や、豊かな生活を目指す意欲を削いでいると感じています。
だからこそ、信頼できる社会保障を実現するために、長年放置されてきた制度の「壁」を打ち壊し、社会保障の根本的な見直しに力を注いでいきます。
-
Q
税金や社会保険料の負担が重いです。負担軽減や公平化のために何をしますか?
A
現在、税金と社会保険料は別々に徴収されており、重複や無駄が生じています。
そのため、これらを一元的に管理する「歳入庁」の設置が必要だと考えています。
歳入庁の設置により、重複や無駄な徴収を防ぎ、行政手続きの効率化と、負担の公平化・軽減を実現してまいります。
-
Q
物価高や円安によって家計が苦しい状況ですが、どのように改善していくべきだと思いますか?
A
食費やエネルギーコストなど、家計を圧迫する物価上昇に対しては、「手元で使えるお金」を増やすことが重要です。
そのために、給料からの天引きを抑えるべく、社会保険料の負担見直しなど、基盤的な構造改革を進めていく必要があります。
あわせて、事業主負担も軽減することで、中小企業の経済活動を後押しし、賃上げにつなげてまいります。
-
Q
子育て政策について、どんな課題認識と改善策を持っていますか?
A
私は、子育てを家庭任せにせず、社会全体で支える制度への転換が必要だと考えています。
現在の子育て支援制度は、専業主婦家庭かフルタイム共働きを前提に設計されており、多様な働き方や家庭のあり方に対応しきれていません。
介護保険制度が、利用者の状況に応じて多様なサービスを選べるように、子育て支援も、「週に2日だけ預けたい」「在宅でシッターを頼みたい」といった多様なニーズに応えられる仕組みが必要です。
さらに、そうした支援を受けるための手続きも、現在のようにわずらわしいものではなく、スマートフォンから簡単に申請できるような環境整備を進めていきます。
-
Q
保育園の入りやすさについて、現状の課題をどう考えますか?
A
現状は点数制による入園可否であり、制度が画一的で柔軟性に欠けます。
地域で支える子育てや在宅育児との両立など、各家庭の事情に合わせた多様な選択肢がある制度へ根本的に作り変えたいと考えています。
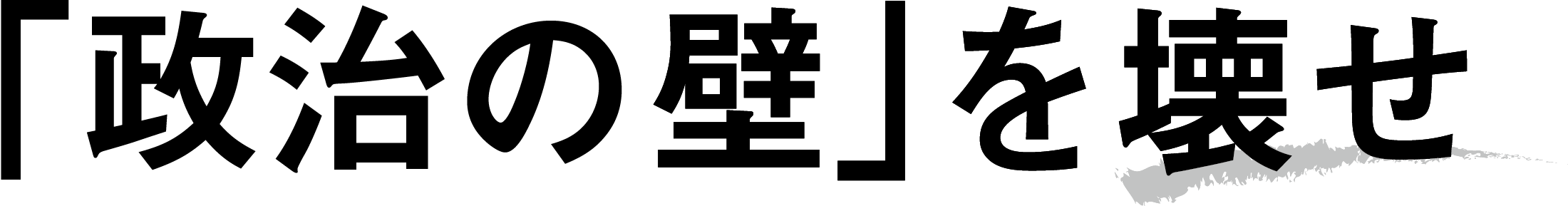
-
Q
給付金など国と自治体の役割分担はどうあるべきですか?
A
給付金をはじめとする一律の行政サービスは、できる限り国が一元的に担う体制へと移行すべきだと考えています。
現場の自治体は、住民対応や地域特性に応じた政策にこそ力を集中すべきです。そのためにも、煩雑な給付金手続きや書類業務は簡素化し、オンラインで一括申請できるような仕組みの一本化を進める必要があります。
もちろん、市と府の連携強化も重要ですが、それ以前に国と地方の役割分担そのものを再整理し、現場が疲弊しない仕組みに改めるべきだと考えます。
-
Q
地方の町が衰退していく不安があります。どのように地域を再生していきますか?
A
住民一人ひとりが、地域ごとの個性や強みを発揮できる環境づくりが重要です。
現状では、インフラや社会保障への予算が膨らみすぎて、本来投資すべき「まちの魅力づくり」に十分な財源が回っていません。
インフラ整備などスケールメリットが働く分野は広域化し、無駄を削減。そこで生まれた財源を、各地域が自らの意思で活用できるようにすることで、「自分たちで町を良くしていける」という環境を整えていきたいと考えています。
「その町をどうするか」は、外から来た人の力を借りることも大切ですが、最終的には住民自身が考え、主役として取り組むべきです。
そのためにも、行政の役割は、住民の挑戦を支える“器”や“構造”を用意することだと考えています。
-
Q
なぜ無所属候補者は政治参加が難しいのですか?
A
現在の選挙制度では、政党が過度に優遇されており、無所属候補にとって選挙活動は圧倒的に不利です。
政見放送やビラの配布、選挙公報など、制度のあらゆる面で政党所属と無所属の間に大きな参入障壁が存在しています。
だからこそ、「しがらみのない候補者」がもっと挑戦しやすくなるよう、政治の構造的な壁を打ち破り、政党や企業・団体献金の論理ではなく、国民一人ひとりの視点に立った政治を実現してまいります。
-
Q
首相公選制(国民が総理を直接選ぶ制度)についてどう考えていますか?
A
私は、首相公選制を導入すべきだと考えています。
現在の総理大臣は国会によって選ばれるため、どうしても永田町の論理に引きずられた政治になりがちです。
しかし、長年続く古い制度に本気でメスを入れるには、主権者である国民が直接選んだリーダーが、大胆な改革に取り組むことが必要です。
そして、その結果に対して国民自身が責任を持ち、納得できる仕組みこそが、民意を反映した政治の第一歩だと考えています。
-
Q
若い人や会社員、普通の市民がもっと政治に参加できるようにするにはどうすればいいですか?
A
私は、若者や会社員など、立場に関わらず誰もが政治に参加しやすい環境づくりが必要だと考えています。
現状では、公職選挙法や政党の構造が高い壁となり、無所属や若手が政治に挑戦しづらい仕組みになっています。これを時代に合った、わかりやすく柔軟な制度に見直すことで、「チャレンジできる政治」を実現していきます。
さらに、日常の中で政治を自分ごととして感じられるよう、政策情報のオープン化やSNS・地域での対話機会の充実など、参加の「ハードルを下げる仕組み」も整えていきたいと考えています。多様な人が関わることでこそ、政治は本当に生活に根ざしたものになるはずです。
-
Q
政治が信頼を取り戻すために必要なことは何だと考えますか?
A
私は、政治資金の透明化が不可欠だと考えています。
大きな組織や特定の利益団体に頼らない、しがらみのない活動を徹底し、政治資金の流れを1円単位でデジタル公開する仕組みを構築していきます。
あわせて、個人による小口寄付をさらに優遇・促進する制度設計を進め、資金面でも「市民が支える政治」の実現を目指します。
政治家が企業や団体ではなく、市民一人ひとりの応援によって活動できることこそ、政治への信頼を取り戻す礎になると考えています。
また、チームもボランティアを中心に構成し、誰もが安心して関われる、開かれた政治をつくっていきます。
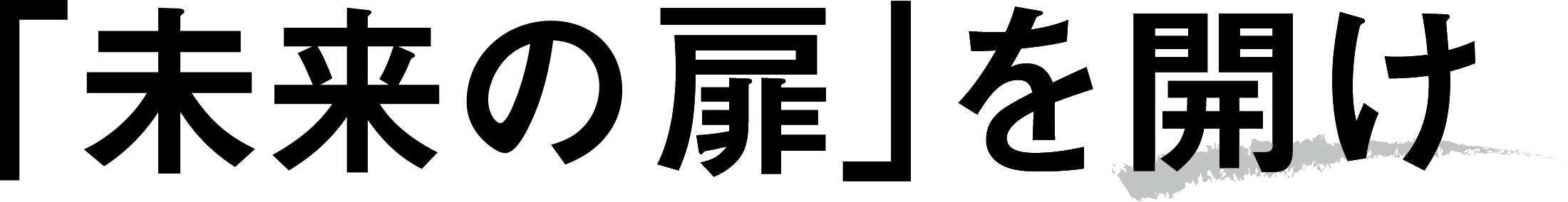
-
Q
教員不足や教育現場の負担について、どう考えていますか?
A
私は、子どもたちの成長にとって、教員の「数」と「質」の確保は何よりも重要だと考えています。
今の教育現場では、産休や退職の代替教員すら足りず、先生たちが疲弊しています。給与水準や待遇も他の専門職と比べて見劣りし、志ある若者が教職を目指しにくくなっている現状があります。
さらに、教育とは関係のない事務処理やクレーム対応など、「教えること」以外の負担が膨れ上がり、授業準備や子どもと向き合う時間すら削られているのが現実です。
私は、そんな現場にこれ以上「自己犠牲」を求めるのではなく、“教えることに専念できる学校”を政治の側が取り戻すべきだと考えます。
そのために、待遇改善や業務の適正化、専門人材の確保といった現場の環境整備に、徹底的に取り組んでまいります。
-
Q
子どもの教育や学びの環境を、今後どう変えていくべきだと考えますか?
A
私は、学校の中だけでなく、社会全体で子どもを育てる環境づくりが重要だと考えています。
まず、教員の「数」と「質」の確保にしっかり取り組み、先生が一人ひとりの子どもと向き合える余裕を取り戻します。あわせて、学校設備の改善や教員の働きやすさ、子どものメンタルサポートなど、教育現場の基盤強化を進めていきます。
そのうえで、「放課後の学び」や「学校外での体験機会」の拡充にも力を入れます。町工場や地域企業、大学との連携を通じて、実社会とつながる学びを広げ、子どもたちが主体的に、そして自然に、自分の可能性を広げられる環境を整えていきます。
-
Q
災害時や救急時の体制強化についてどう考えていますか?
A
私は、災害や救急時に命を守るための「消防・救急体制の強化」と「上下水道インフラの老朽化対策」が、最優先の課題だと考えています。
消防・救急については、広域化によって指令体制や装備を強化し、救急搬送の遅れや逼迫を防ぐ体制づくりに取り組みます。
また、上下水道については、多くの地域で老朽化が進んでおり、大規模災害時には断水や衛生リスクが現実のものになります。計画的な更新投資と、広域化による効率化を進めることで、安全で持続可能なライフラインを次の世代に引き継ぐ責任を果たしていきます。
-
Q
「虐待やいじめの早期発見」「困ったときの相談場所」について、行政はどう取り組むべきですか?
A
行政は、虐待やいじめの兆候を見逃さず、困ったときに誰もが安心して相談できる体制を整える責任があります。
働き手の減少やベテラン職員の退職などにより、現場の対応力が弱まる中でも、支援を継続できるようにするために、AIやデータの活用による早期発見・支援体制の構築が不可欠だと考えています。
子どものSOSを見逃さない仕組みづくりや、誰もがアクセスしやすい相談窓口の整備に、これからも継続的に取り組んでいきます。
-
Q
日本における外国人受け入れ政策の課題と今後の方向性は何ですか?
A
日本では、「移民政策はとっていない」と政府が表明する一方で、現実には外国人労働者や在留外国人の数が年々増加しています。
しかし、受け入れ体制の整備が追いついておらず、教育・福祉・地域社会などの負担が自治体に偏っていることが大きな課題です。特に、現場を担う自治体が制度の不備によって疲弊している現状は、早急に見直すべきだと考えます。
私は今後、国としての責任を明確にし、外国人受け入れに関する総量規制(人数の上限設定)や、分野・条件を明確にした受け入れルールの策定が不可欠だと考えています。地方任せではなく、国が制度設計と財源を担う体制への転換が必要です。
-
Q
大阪の発展や未来に向けて、どのようなビジョンや具体的な取組みが必要だと考えていますか?
A
私は、大阪がこれからも成長を続けるためには、国際競争力の強化と、地域産業の底上げの両方が必要だと考えています。
まず、関西空港と港湾を一体で整備することで、空と海の物流ネットワークを効率化し、アジアに開かれた国際都市・大阪の基盤を強化します。また、IR(統合型リゾート)の利益を地元に還元する仕組みづくりなども進め、都市の持続的な成長を支えます。
一方で、地域のものづくりを支える町工場には、産業と教育の連携を通じて技術継承と若手人材の確保を後押しします。中小企業が持つ高度な技術を次の世代に引き継ぎ、教育機関との協働によって新たな価値創出につなげる仕組みをつくります。
大阪の伝統と先端をつなぎ、地域の強みを未来につなぐ産業基盤を築いていきます。
年金だけで老後は安心して暮らせますか?
年金財政を重視した結果、目減りが続く現行の年金制度では、老後に安心して生活することは難しいと考えています。
そのため、物価と連動して底上げされる「最低保障年金」を確立し、年金の「財政」ではなく、年金による「生活」を守る制度への転換が必要です。
また、年金は本来「仕送り方式」(賦課方式)で、現役世代が高齢者を支える仕組みでしたが、人口ピラミッドの変化により若い世代が減り、仕送りだけでは支えきれなくなっています。
そもそも、私的年金である3階部分(確定拠出年金など)がなければ老後生活が成り立たないという公的年金の現状に、私は大きな違和感を覚えています。
今後は、積立方式への段階的移行などを着実に進め、受給不安の解消に取り組むべきだと考えています。
社会保障について、これからどう改善していくつもりですか?
私は、社会保障に対する「不安の壁」を壊すことが、最も重要だと考えています。
現状では、年金をはじめとする社会保障制度への信頼が失われており、それが暮らしへの安心感や、豊かな生活を目指す意欲を削いでいると感じています。
だからこそ、信頼できる社会保障を実現するために、長年放置されてきた制度の「壁」を打ち壊し、社会保障の根本的な見直しに力を注いでいきます。
税金や社会保険料の負担が重いです。負担軽減や公平化のために何をしますか?
現在、税金と社会保険料は別々に徴収されており、重複や無駄が生じています。
そのため、これらを一元的に管理する「歳入庁」の設置が必要だと考えています。
歳入庁の設置により、重複や無駄な徴収を防ぎ、行政手続きの効率化と、負担の公平化・軽減を実現してまいります。
物価高や円安によって家計が苦しい状況ですが、どのように改善していくべきだと思いますか?
食費やエネルギーコストなど、家計を圧迫する物価上昇に対しては、「手元で使えるお金」を増やすことが重要です。
そのために、給料からの天引きを抑えるべく、社会保険料の負担見直しなど、基盤的な構造改革を進めていく必要があります。
あわせて、事業主負担も軽減することで、中小企業の経済活動を後押しし、賃上げにつなげてまいります。
子育て政策について、どんな課題認識と改善策を持っていますか?
私は、子育てを家庭任せにせず、社会全体で支える制度への転換が必要だと考えています。
現在の子育て支援制度は、専業主婦家庭かフルタイム共働きを前提に設計されており、多様な働き方や家庭のあり方に対応しきれていません。
介護保険制度が、利用者の状況に応じて多様なサービスを選べるように、子育て支援も、「週に2日だけ預けたい」「在宅でシッターを頼みたい」といった多様なニーズに応えられる仕組みが必要です。
さらに、そうした支援を受けるための手続きも、現在のようにわずらわしいものではなく、スマートフォンから簡単に申請できるような環境整備を進めていきます。
保育園の入りやすさについて、現状の課題をどう考えますか?
現状は点数制による入園可否であり、制度が画一的で柔軟性に欠けます。
地域で支える子育てや在宅育児との両立など、各家庭の事情に合わせた多様な選択肢がある制度へ根本的に作り変えたいと考えています。
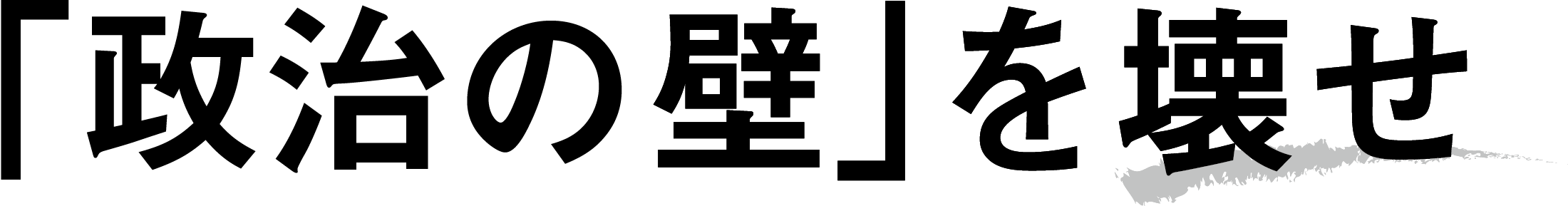
-
Q
給付金など国と自治体の役割分担はどうあるべきですか?
A給付金をはじめとする一律の行政サービスは、できる限り国が一元的に担う体制へと移行すべきだと考えています。
現場の自治体は、住民対応や地域特性に応じた政策にこそ力を集中すべきです。そのためにも、煩雑な給付金手続きや書類業務は簡素化し、オンラインで一括申請できるような仕組みの一本化を進める必要があります。
もちろん、市と府の連携強化も重要ですが、それ以前に国と地方の役割分担そのものを再整理し、現場が疲弊しない仕組みに改めるべきだと考えます。 -
Q
地方の町が衰退していく不安があります。どのように地域を再生していきますか?
A住民一人ひとりが、地域ごとの個性や強みを発揮できる環境づくりが重要です。
現状では、インフラや社会保障への予算が膨らみすぎて、本来投資すべき「まちの魅力づくり」に十分な財源が回っていません。
インフラ整備などスケールメリットが働く分野は広域化し、無駄を削減。そこで生まれた財源を、各地域が自らの意思で活用できるようにすることで、「自分たちで町を良くしていける」という環境を整えていきたいと考えています。
「その町をどうするか」は、外から来た人の力を借りることも大切ですが、最終的には住民自身が考え、主役として取り組むべきです。
そのためにも、行政の役割は、住民の挑戦を支える“器”や“構造”を用意することだと考えています。 -
Q
なぜ無所属候補者は政治参加が難しいのですか?
A現在の選挙制度では、政党が過度に優遇されており、無所属候補にとって選挙活動は圧倒的に不利です。
政見放送やビラの配布、選挙公報など、制度のあらゆる面で政党所属と無所属の間に大きな参入障壁が存在しています。
だからこそ、「しがらみのない候補者」がもっと挑戦しやすくなるよう、政治の構造的な壁を打ち破り、政党や企業・団体献金の論理ではなく、国民一人ひとりの視点に立った政治を実現してまいります。 -
Q
首相公選制(国民が総理を直接選ぶ制度)についてどう考えていますか?
A私は、首相公選制を導入すべきだと考えています。
現在の総理大臣は国会によって選ばれるため、どうしても永田町の論理に引きずられた政治になりがちです。
しかし、長年続く古い制度に本気でメスを入れるには、主権者である国民が直接選んだリーダーが、大胆な改革に取り組むことが必要です。
そして、その結果に対して国民自身が責任を持ち、納得できる仕組みこそが、民意を反映した政治の第一歩だと考えています。 -
Q
若い人や会社員、普通の市民がもっと政治に参加できるようにするにはどうすればいいですか?
A私は、若者や会社員など、立場に関わらず誰もが政治に参加しやすい環境づくりが必要だと考えています。
現状では、公職選挙法や政党の構造が高い壁となり、無所属や若手が政治に挑戦しづらい仕組みになっています。これを時代に合った、わかりやすく柔軟な制度に見直すことで、「チャレンジできる政治」を実現していきます。
さらに、日常の中で政治を自分ごととして感じられるよう、政策情報のオープン化やSNS・地域での対話機会の充実など、参加の「ハードルを下げる仕組み」も整えていきたいと考えています。多様な人が関わることでこそ、政治は本当に生活に根ざしたものになるはずです。 -
Q
政治が信頼を取り戻すために必要なことは何だと考えますか?
A私は、政治資金の透明化が不可欠だと考えています。
大きな組織や特定の利益団体に頼らない、しがらみのない活動を徹底し、政治資金の流れを1円単位でデジタル公開する仕組みを構築していきます。
あわせて、個人による小口寄付をさらに優遇・促進する制度設計を進め、資金面でも「市民が支える政治」の実現を目指します。
政治家が企業や団体ではなく、市民一人ひとりの応援によって活動できることこそ、政治への信頼を取り戻す礎になると考えています。
また、チームもボランティアを中心に構成し、誰もが安心して関われる、開かれた政治をつくっていきます。
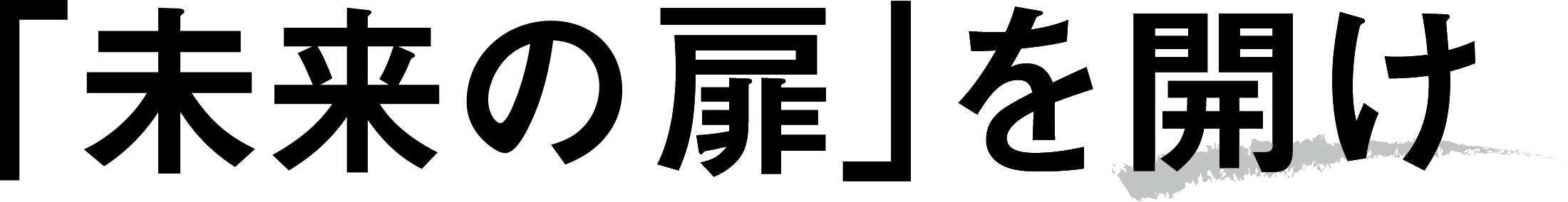
-
Q
教員不足や教育現場の負担について、どう考えていますか?
A
私は、子どもたちの成長にとって、教員の「数」と「質」の確保は何よりも重要だと考えています。
今の教育現場では、産休や退職の代替教員すら足りず、先生たちが疲弊しています。給与水準や待遇も他の専門職と比べて見劣りし、志ある若者が教職を目指しにくくなっている現状があります。
さらに、教育とは関係のない事務処理やクレーム対応など、「教えること」以外の負担が膨れ上がり、授業準備や子どもと向き合う時間すら削られているのが現実です。
私は、そんな現場にこれ以上「自己犠牲」を求めるのではなく、“教えることに専念できる学校”を政治の側が取り戻すべきだと考えます。
そのために、待遇改善や業務の適正化、専門人材の確保といった現場の環境整備に、徹底的に取り組んでまいります。
-
Q
子どもの教育や学びの環境を、今後どう変えていくべきだと考えますか?
A
私は、学校の中だけでなく、社会全体で子どもを育てる環境づくりが重要だと考えています。
まず、教員の「数」と「質」の確保にしっかり取り組み、先生が一人ひとりの子どもと向き合える余裕を取り戻します。あわせて、学校設備の改善や教員の働きやすさ、子どものメンタルサポートなど、教育現場の基盤強化を進めていきます。
そのうえで、「放課後の学び」や「学校外での体験機会」の拡充にも力を入れます。町工場や地域企業、大学との連携を通じて、実社会とつながる学びを広げ、子どもたちが主体的に、そして自然に、自分の可能性を広げられる環境を整えていきます。
-
Q
災害時や救急時の体制強化についてどう考えていますか?
A
私は、災害や救急時に命を守るための「消防・救急体制の強化」と「上下水道インフラの老朽化対策」が、最優先の課題だと考えています。
消防・救急については、広域化によって指令体制や装備を強化し、救急搬送の遅れや逼迫を防ぐ体制づくりに取り組みます。
また、上下水道については、多くの地域で老朽化が進んでおり、大規模災害時には断水や衛生リスクが現実のものになります。計画的な更新投資と、広域化による効率化を進めることで、安全で持続可能なライフラインを次の世代に引き継ぐ責任を果たしていきます。
-
Q
「虐待やいじめの早期発見」「困ったときの相談場所」について、行政はどう取り組むべきですか?
A
行政は、虐待やいじめの兆候を見逃さず、困ったときに誰もが安心して相談できる体制を整える責任があります。
働き手の減少やベテラン職員の退職などにより、現場の対応力が弱まる中でも、支援を継続できるようにするために、AIやデータの活用による早期発見・支援体制の構築が不可欠だと考えています。
子どものSOSを見逃さない仕組みづくりや、誰もがアクセスしやすい相談窓口の整備に、これからも継続的に取り組んでいきます。
-
Q
日本における外国人受け入れ政策の課題と今後の方向性は何ですか?
A
日本では、「移民政策はとっていない」と政府が表明する一方で、現実には外国人労働者や在留外国人の数が年々増加しています。
しかし、受け入れ体制の整備が追いついておらず、教育・福祉・地域社会などの負担が自治体に偏っていることが大きな課題です。特に、現場を担う自治体が制度の不備によって疲弊している現状は、早急に見直すべきだと考えます。
私は今後、国としての責任を明確にし、外国人受け入れに関する総量規制(人数の上限設定)や、分野・条件を明確にした受け入れルールの策定が不可欠だと考えています。地方任せではなく、国が制度設計と財源を担う体制への転換が必要です。
-
Q
大阪の発展や未来に向けて、どのようなビジョンや具体的な取組みが必要だと考えていますか?
A
私は、大阪がこれからも成長を続けるためには、国際競争力の強化と、地域産業の底上げの両方が必要だと考えています。
まず、関西空港と港湾を一体で整備することで、空と海の物流ネットワークを効率化し、アジアに開かれた国際都市・大阪の基盤を強化します。また、IR(統合型リゾート)の利益を地元に還元する仕組みづくりなども進め、都市の持続的な成長を支えます。
一方で、地域のものづくりを支える町工場には、産業と教育の連携を通じて技術継承と若手人材の確保を後押しします。中小企業が持つ高度な技術を次の世代に引き継ぎ、教育機関との協働によって新たな価値創出につなげる仕組みをつくります。
大阪の伝統と先端をつなぎ、地域の強みを未来につなぐ産業基盤を築いていきます。
教員不足や教育現場の負担について、どう考えていますか?
私は、子どもたちの成長にとって、教員の「数」と「質」の確保は何よりも重要だと考えています。
今の教育現場では、産休や退職の代替教員すら足りず、先生たちが疲弊しています。給与水準や待遇も他の専門職と比べて見劣りし、志ある若者が教職を目指しにくくなっている現状があります。
さらに、教育とは関係のない事務処理やクレーム対応など、「教えること」以外の負担が膨れ上がり、授業準備や子どもと向き合う時間すら削られているのが現実です。
私は、そんな現場にこれ以上「自己犠牲」を求めるのではなく、“教えることに専念できる学校”を政治の側が取り戻すべきだと考えます。
そのために、待遇改善や業務の適正化、専門人材の確保といった現場の環境整備に、徹底的に取り組んでまいります。
子どもの教育や学びの環境を、今後どう変えていくべきだと考えますか?
私は、学校の中だけでなく、社会全体で子どもを育てる環境づくりが重要だと考えています。
まず、教員の「数」と「質」の確保にしっかり取り組み、先生が一人ひとりの子どもと向き合える余裕を取り戻します。あわせて、学校設備の改善や教員の働きやすさ、子どものメンタルサポートなど、教育現場の基盤強化を進めていきます。
そのうえで、「放課後の学び」や「学校外での体験機会」の拡充にも力を入れます。町工場や地域企業、大学との連携を通じて、実社会とつながる学びを広げ、子どもたちが主体的に、そして自然に、自分の可能性を広げられる環境を整えていきます。
災害時や救急時の体制強化についてどう考えていますか?
私は、災害や救急時に命を守るための「消防・救急体制の強化」と「上下水道インフラの老朽化対策」が、最優先の課題だと考えています。
消防・救急については、広域化によって指令体制や装備を強化し、救急搬送の遅れや逼迫を防ぐ体制づくりに取り組みます。
また、上下水道については、多くの地域で老朽化が進んでおり、大規模災害時には断水や衛生リスクが現実のものになります。計画的な更新投資と、広域化による効率化を進めることで、安全で持続可能なライフラインを次の世代に引き継ぐ責任を果たしていきます。
「虐待やいじめの早期発見」「困ったときの相談場所」について、行政はどう取り組むべきですか?
行政は、虐待やいじめの兆候を見逃さず、困ったときに誰もが安心して相談できる体制を整える責任があります。
働き手の減少やベテラン職員の退職などにより、現場の対応力が弱まる中でも、支援を継続できるようにするために、AIやデータの活用による早期発見・支援体制の構築が不可欠だと考えています。
子どものSOSを見逃さない仕組みづくりや、誰もがアクセスしやすい相談窓口の整備に、これからも継続的に取り組んでいきます。
日本における外国人受け入れ政策の課題と今後の方向性は何ですか?
日本では、「移民政策はとっていない」と政府が表明する一方で、現実には外国人労働者や在留外国人の数が年々増加しています。
しかし、受け入れ体制の整備が追いついておらず、教育・福祉・地域社会などの負担が自治体に偏っていることが大きな課題です。特に、現場を担う自治体が制度の不備によって疲弊している現状は、早急に見直すべきだと考えます。
私は今後、国としての責任を明確にし、外国人受け入れに関する総量規制(人数の上限設定)や、分野・条件を明確にした受け入れルールの策定が不可欠だと考えています。地方任せではなく、国が制度設計と財源を担う体制への転換が必要です。
大阪の発展や未来に向けて、どのようなビジョンや具体的な取組みが必要だと考えていますか?
私は、大阪がこれからも成長を続けるためには、国際競争力の強化と、地域産業の底上げの両方が必要だと考えています。
まず、関西空港と港湾を一体で整備することで、空と海の物流ネットワークを効率化し、アジアに開かれた国際都市・大阪の基盤を強化します。また、IR(統合型リゾート)の利益を地元に還元する仕組みづくりなども進め、都市の持続的な成長を支えます。
一方で、地域のものづくりを支える町工場には、産業と教育の連携を通じて技術継承と若手人材の確保を後押しします。中小企業が持つ高度な技術を次の世代に引き継ぎ、教育機関との協働によって新たな価値創出につなげる仕組みをつくります。
大阪の伝統と先端をつなぎ、地域の強みを未来につなぐ産業基盤を築いていきます。